目次
吃音を誤って学習してしまった
吃音者の中に、人の吃音のまねをしていたらいつの間にか自分も吃音になってしまった、という人がいます。人間には、生まれつき人にチューニング(同調)する本能が備わっています。
生後間もない赤ちゃんの前でお母さんが舌を出すと、赤ちゃんも口をムニャムニャ動かして舌を出そうとします。赤ちゃんに微笑みかけると、つられたようにニコッとします。また、長年仲良く一緒に暮らしている夫婦は、次第に表情も話し方もよく似てくる、と言われます。

私たちは皆、言葉を話すことができます。しかし、お母さんにも家族の誰からも、声の出し方について教わってはいません。「声を出すには息が必要ですよ」「横隔膜で押し出した息で声帯を震動させなさい」「ただ声帯を震動させるだけでは言葉になりません。
震動させた声を、鼻や口に響かせて!」「アは、口を大きくあけて…」などと教えられて“うま、うま”“まま”などと言えるようになったわけではありません。赤ちゃんは、呼吸を意識したり、口の動かし方や声帯の使い方を意識することなく、お母さんやお父さんの口を見て、声を耳で聞き、全体の声の出し方を潜在意識が感じとって体で覚えたのです。
勿論、人間の大脳には先天的に話せる能力はありますが、それに後天的な要素が加わらなければ、やはり話せるようにはなりません。しかも言語習得には時期があって、脳発育の旺盛な幼少期に第一歩をふみださないと、その後の習得はきわめて困難です。オオカミに育てられたという特別な例ではいうまでもありませんが、小さい時から耳の聞こえない子どもが言語が話せないのは、他人の声が聞こえないから模倣ができないのです。
ところが、両親、あるいは自分を主に育ててくれる人が吃音であったり、早口であったりしたらどうなるか。当然吃音をそのまま体で覚えてしまったり、早口を身につけたり、未熟な発語器官が追いつかず、たどたどしい焦った話し方が固定してしまうことだって考えられます。
しかし、このケースは比較的少ないと思われます。なぜなら、大抵の吃音者は緊張していない時や吃音を意識していない時にはどもらずに話せることが多いものです。ということは、ほとんどの吃音者は他の人と同様に、ちゃんとした話し方を学習してはいるが、緊張したり意識したりすると、その話し方が自然に出てこない状態だと言えます。
聴覚フィードバック機構の故障からどもる
私たちは話しをする場合、聴覚フィードバック機構がしっかり働いています。絶えず、無意識的に自分自身の声を耳で聞き、監視し点検して自分の声の大きさや速さ、リズム、声の調子や印象などをその場に応じて調整しているのです。
唖者がしゃべれないのは、耳が聞こえないからであり、耳が遠い人は大きな声で話すことからも、話すことと耳は非常に重要な関係があることがわかります。
健康な人は、聴覚フィードバックに約0,01秒の遅れがあると言われます。すなわち、声帯で発生した声が口から出て、自分の耳から入って脳の聴覚中枢に到達するのにおおよそ0,01秒かかるのです。早口を素因としている吃音者の場合は、特に早く話そうとするあまり、自分の声を耳でしっかりと聞かないうちに次の声を発声しようとしてまごついてしまいます。その結果、つまる、連発するなどの吃音症状が現れます。
吃音の人はこの通常身についているはずの聴覚フィードバックの働き(0,01秒遅れの声をモニターすること)が十分に働いていないため非流暢性が出現してしまうわけです。
過度のモニタリングでどもる
非吃音者は、音を構え作る努力は一切していません。思ったとおりに口を動かせば願ったとおりの音声が出てきます。すなわち言語行動とは、呼吸運動や歩行運動、書字運動と同じ種類のもので、もともとは自動運動と呼ばれ、自動化されている行動なのです。
自動化されている運動に、過剰な干渉を向けると「けいれん」がおきやすいという人間行動の原理は、よく吃音現象を説明しているといえます。
どもらないで喋ろうとする気持ちから、声を意識的にコントロールしようと自動化されている言語行動に過剰な監視を向け、正常者では無意識的に行われている聴覚フィードバックが意識的に行われています。
ここで非常に重大な問題が生じてきます。というのは、意識的に声をコントロールしようとすると、注意は声として口から出す前にコントロールしなくてはなりません。そこで声に出す前に口の中で声を出してみて、ちゃんと喋れそうかどうか口の形や舌の位置、のどの緊張や動き方等、発語器官の運動感覚を意識しながら話しています。自動化されているはずの言語行動を意識して動かすのですから、自然には働かずガタガタになってしまいます。
もしこのように意識して発声した言葉が、例えどもらずに言えたとしても、意識してコントロールしている限り、不自然であり、他の人とは違う、つまり自分は「どもり」であるという思いから開放されることがありません。
またもう一つの重大な問題は、口から発した声が耳から入り、聴覚中枢に到達するのに約0,01秒かかりますが、一方発声した声は体の内部から骨伝導でほぼ同時に直接聴覚に達しているのです。しかし、私たちは話す時に必要な聴覚フィードバックは、外に出た声を耳から聞く、つまり約0,01秒遅れの声をモニターすることなのです。ところが吃音の人は、早くコントロールしようとし過ぎるからか、約0,01秒前に聞こえる骨伝導の声に聴覚の焦点を合わせているのです。
したがって、意識して動かして発した声を骨伝導で聞き取り、同時に調節しようとするために、非常にぎこちないものになってしまいます。しかもそのぎこちない声が、約0,0一秒後に耳から聞こえる訳ですから、その遅れた声にも反応して混乱し、ますます必死に発語の筋肉を意識的に操作しなければならなくなるのです。
このことは、DAF(音声遅延フィードバック装置)で正常者に、自分の話す音声を遅らせて聞かせる。つまり、吃音と同じ条件を作ると、非吃音者も途端に吃音者のようになってしまいます。このことからも吃音者は、音声をコントロールするためにモニターする焦点が、耳から遅れて入ってくる音声に合わせられていないことが分かります。
不安反応を学習したことでどもる
幼児期の親子関係のあり方が吃音の発症に関連があることは、従来から指摘されてきたことです。吃音がみられない子供の自然な母子の対話面では、母親は話し方そのものに注目せず、子供の表現したい、あるいは伝達したい内容、つまり話し言葉の内容に注目して対応しており、子供は、母親の対応の仕方から違和感とか不快感を感じることはありません。子供の話し方に話し言葉の非流暢性がみられるよになっても、ごく初期のこれを母親が気にとめない間は、母子の対話状況には特別な変化は生じません。
しかし、吃音に気づくとともに、母親と子供の対話状況は変化していきます。母親は子供の話し方に注目し、緊張した態度を示すようになり、子供はそれに違和感を持つようになる。この状況が積み重ねられるにしたがい、より悪化した状況が見られるようになります。母親は子供全体をみる余裕がなくなり、話し言葉のみに固着して子供をみるようになって、話し方のみに注目し、話し方を拒否したり、話し方に対する干渉を示し、緊張を示す態度や不安や嫌悪などの感情を伴って応対するようになっていきます。
子供が言葉を覚えていく過程で、誰でも時にはどもるわけですが、心配症の親達が犯す最大の誤りは、「はっきりしゃべりなさい!」「もっとゆっくり」「そうじゃないでしょう…でしょう!」と注意しますが、問題はその時の親の心の中の、子供に対する感情的判断の部分です。「こんなこともちゃんと喋れないの?どうしようもない子ね」「どもりになったらどうしよう…」「ほんとにダメねえ!」等と、どもるだけで“ダメな子”と全人格的な評価を下したり「ちゃんと喋れないんだから!」等、“お前は吃音である”と暗に教え込んでしまうことです。

ひどい場合には、暗に表情や声の調子や態度に出てしまうのではなく、言葉でもはっきり言ってしまう親もいます。こうなると子供にとってどもることは、単にどもったという一つの出来事ではなく、「また“ダメなやつ”と思われてしまった」とひどく傷つきます。ちゃんと話さなければ自分が聞いて欲しいことや、言いたい気持ちを受け入れてもらえない、つまり自分の言いたいことや自分の気持ちよりも、話し方の方が大事に扱われ、無価値な自分を感じ、二重のショックを受けることになります。
子供にとっては、喋ることは恐怖となり、ちゃんと喋れることは、ただ喋れたということではなく、自分の考えや気持ち、すなわち自分自身を受け入れてもらえるかどうかという、非常に重大な意味を持つことになります。
こうして子供は、人に喋ることに対して特別な感情を持ち、そうした場面やどもりやすい特定の言葉を恐れるようになります。話すことの本来の目的-話すことは人とのコミュニケーションであり、自分の考えや気持ちを言葉にして伝える-ことから、どもるかどもらないかに最大の価値をおくことになり、話すことを特別に意識し緊張を呼ぶことになるのです。
では子供の頃、話すことを特別注意されなかったり、むしろ話し方をほめられた人は決して吃音にはならないか、というとそうとばかりは言えません。ほめられることも自分の考えや気持ちより、話し方を重要に扱うことと同じになり、特別な感情を持つ場合があります。
また、「話す」ことについてなんら問題がなく育っても、不安や不満が大きく自分が人に認められたい要求が強い場合、あるいは、自分に対して完全を求め、ささいなミスを許せないような性格が原因することもあります。
初期の段階では、子どもは吃音を自覚していないことが多いです。ところが、その症状が顕著になり、言葉がつかえて思うように出ない、スムーズにしゃべれないことがたび重なると、本人も自分の状態に気づくようになります。最初は話すことに伴う生理的不快感として、驚きや不安と共に漠然と自覚するものです。これはどもっている最中に経験する一時的な感情であり、尾を引くことはまだありません。
吃音がさらに進むと、言葉を話そうとする時、あるいは話している途中で、突然のどが閉まり、舌がもつれ、口唇がこわばり話せない状態になると、本人にとっては大変なショックであり、自分の力ではどうすることもできないような無力感や絶望感に襲われてしまいます。そして一刻も早くその状態から抜け出そうとしてあせったり、もがいたりすることになります。さらにこの時の聞き手の反応が、前述のように本人にとって罰刺激となるようなものであれば、一層苦しい不快な体験として恐れるようになります。この時の罰刺激となるものは、聞き手の苛立ち、責め、注意、嘲笑などです。吃音に対して批判的、拒否的態度を示す人、無理解で冷たい感じの人の前では、どもりの症状はふつう悪化するようです。
非吃音者な人ですら、驚き、憤り、怒り、喜びなどの強い感情や情動を表現する時に、かなり明らかな吃音の症状が起こることは、日常しばしば経験するところです。したがって、吃音の原因の一つに、情動的緊張をあげることを決して忘れてはならないのです。
吃音の原因論で、アメリカのウェンデル・ジョンソンの「診断起因説」が長い間最も支持され、絶大な人気を保ってきたのは、聞き手から受ける印象や対人関係に影響されて変動する様子が実際に観察されるからです。
ウェンデル・ジョンソンの診断起因説
ジョンソンの診療室に、親に連れてこられた“どもりがち”とされた子供たちに、1000語の言葉テストをしたところ、個人による差異はあっても平均して415語に非流暢性が発見されました。
ジョンソンは比較群として「家の子供の言葉には問題がない」とされた同年代の子を集めて、全く同じ言葉テストをしたところ、非流暢性はやはり平均四十五語でした。このことから、ジョンソンは、『吃音は初めにあるのではなく、発達上あたりまえのつかえを“吃音”と診断することから“吃音”は始まる』と診断起因説を発表したのです。

例えば、電話をかけた時にどもると、どもったいやな感情の記憶が残ります。すると次に電話をかけようとすると、前にどもったいやな経験が思い出され、「また、どもってあのいやな思いをするのでは」と恐れます。その恐怖は肉体を緊張させ、どもらないように意識することで、結局恐れた通りの吃音症状を引き起こしてしまいます。
その結果、ますます電話をかけることが恐くなり、徐々に電話をかけることを避けるようになります。避けているので、どうしても電話をかけなければならない状況になった時は、更に不安や恐怖心は増大することになります。
電話-どもる-失敗の予期-恐怖-回避-どもる の条件反射の回路ができ上がってしまうのです。つまり、吃音は不安反応を学習したことで起こる条件づけられた行動とみることができます。
幼児時代に始まった正常範囲内のことばのつまづきを、その都度監視して、やり直しを命じたり、大声で怒鳴ったり、体罰を加えたり、嘲笑したり、拒否することで、それが罰刺激となって、そういう思いをしたくないと、どもることを回避しようとする行動が始まります。どもりそうな予感が有ると、罰を受けまいと、一生懸命どもるまいと努力します。この時、発語行動にはストップがかかることになります。なぜなら、吃音を知られて罰を受けたくないのですから、言おうとする意志より、避けて言わない意志の方が勝ってしまうからです。この状態が難発現象です。
発声器官の調整がうまくいかない時にどもる
発声、発語の中枢は脳にあります。脳の中で話そうという意図や、その内容が作られ、それが形式を整え、話すための運動のプログラムができ上がり、運動の中枢経路を通って末梢の発声、発語器官へと送られてゆくのです。ですから、例えば、前頭葉の「言語」の領域が脳出血や脳梗塞などで壊れてしまうと、発声、発語に必要な筋肉に麻痺がなくても、声を言葉に組み立てて話すことができなくなってしまいます。(ブローカ失語という)
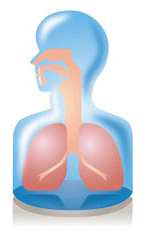
もちろん吃音の方は脳の働きには全く異常はありません。では発声のメカニズムですが、私たちが何かをしゃべろうとしますと、人間の喉には左右に声帯と呼ばれる膜がありますが、これが縮まろうとしてきます。そこを肺から気管支、気管を通ってきた息が左右の声帯を押し広げようとして吹き出してくると音が発声します。この時の音は、喉頭原音と呼ばれ、雑音に近い不快な響を持った音です。これを人間らしい音に変えてゆくのが、舌や唇、あごなどの動きと、共鳴の働きです。
吃音の人は声帯、舌、口、口唇など、それぞれの器官の働きは全く正常なのですが、相互のタイミング調整が一時的にうまくいかないために、吃音が生じるのです。例えば、吃音の人の難発状態ですが、声を出す為には声帯が縮まる必要が有りますが、発語に対する緊張の為に喉に力が入って過度に声帯を閉じてしまうと息を送り出して声帯を押し広げることができない為に声が作られない訳です。
また、語のもつれやくり返しは、声帯の開閉運動と、人の耳に聞こえる音を作り出すための運動(口やあごや舌の動き 構音運動という)とのタイミングがずれてしまった時に起こりやすいようです。
発声からみた原因
私たちは、正しい発音については家庭ではもちろん、小学校、中学校でもあまり教わっていません。発音というのは、ただ単に口の開け方や舌の動かし方だけを言うのではなく、“息を加工して外に送り出す”という一連の流れを伴っています。
この「流れ」とは「息の流れ」を言います。すなわち発声とは、息の流れを伴うものなのだ、ということなのです。ところが、この大切な「息の流れ」を妨げるものが、私たちの日本語の中にあるのです。(諸外国にはあまりない)それは、小さい「っ」と「ん」なのです。
小さい「っ」は、「言った」「買った」「行った」などの真ん中のつまった音を言います。この小さい「っ」も、日本語の中では他の仮名文字一字と同じ一拍分の質量を持っています。「ど、も、り」は三拍で、買ったは「かっ、た」となり同じ三拍です。そしてこれを声を出して読んでみると、この小さな「っ」で息の流れは完全に止まってしまうことが分かります。それに何となく、舌やのどに力が入っているのが分かります。
また、この小さい「っ」の後には、「か行」「た行」「ぱ行」などの破裂音がくることも多く、ますます息の流れを止めることになり、それに伴って舌やのどにさらに強い力みが生じて、非常にどもりやすくなってしまいます。
破裂音の場合の息の流れの閉鎖は、あくまで一瞬のことなのですが、この小さな「っ」は、会話の中で一拍分息の流れを完全に止めてしまいます。本来自然に流れなければならない息が、知らず知らずの内にぶつ切れになって、発語器官に緊張を呼ぶことになっているのです。
破裂音そのものを苦手とする吃音の人が多いのも、このように息の流れが止められてしまうことが原因していることも多いのです。また、特に吃音の人に「か行」「た行」を苦手とする人が多いのも、「か行のkの部分」「た行のtの部分」が言葉の初めにくると、一瞬息の流れが止まることが考えられるのです。反対に「言った」「買った」を「言いました」「買いました」と言い換えると、とても言いやすく、流れが止められないからだということが分かります。
また、「ん」も小さい「っ」と同様、一拍分息の流れが止まろうとします。例えば、「ほんもの」「しんぱい」など。一拍分息の流れが止まって、そして、舌やのどにわずかだけども力が入るものです。この「っ」「ん」の一拍分の独立した音は、日本語の特徴でもあるのです。
もう一つ重大な問題として、この破裂音や鼻音は舌で息を止めはするものの、その直前までは息は流れていなくてはなりません。ところが、よく注意して観察して見ると、吃音の人は声帯で息を止めているのです。つまり、最も自然な息の流れが必要な声帯で呼吸を調節するのが当り前になっているのです。すなわち吃音は、息の自然な流れを一瞬止めなければならない発音(「っ」や「ん」、そして「か行のkの部分」「た行のtの部分」)に対して声帯で息を止める習慣ができ上がり、本来舌や唇で止めている流れを、息で前に弾いて発音するのに、その奥の声帯で息が止まっているために、舌や唇を弾くことができなくなってしまっているのです。